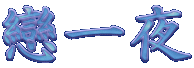
其の七
神が許した最後の我儘が、この美しい夢だというならば
神よ、あなたほど残酷な創造主はいないだろう
これほど甘美な罰もないだろう
それでもまだ、あなたへと願う この私の愚かさよ
玉の緒が夜明けまで耐えんことを
この夢が朝まで潰えんことを
まるで壊れ物を扱う手付き。
佐為は自分を仰向けに寝かせるという動作を、これほどまでに注意深く行われたことはないかもしれないと、一人胸の内側で苦笑する。勿論、それはこの上なく好ましいことであったが、酷く切ないことでもあった。
柔らかく寝かされた布団の上から見上げると、行洋の視線と鉢遭った。
白い寝具の上に広がる色鮮やかな絹と乱れた髪。
その美しく淫猥な絵を味わうのは一夜の夢に相応しいけれど。
不意に行洋の胸を、たとえようのない感情が襲ったのは、同じ瞬間はもう二度と訪れないと、腹立たしいほどに分かっているから。
哀しいような色をしたその瞳が自分を見詰めているのを感じた瞬間、佐為は知らずに己が手を伸ばしていた。乱れた単から逃れたその手が呼ぶがまま、行洋は静かに身を沈めて行く。
顔を近づけ、長い睫毛に守られた瞳を覗き込む。
そこにあった思いがけず強い力をもった瞳に、行洋は驚いて身体の動きを止めた。
生まれ始めた熱に潤んだ瞳を見せながら、それでも佐為は目を逸らさない。
二人は吐息を感じるほどの距離で、ただ見詰めあった。情事は既に始まっていると、どちらもが認知しているにも関わらず。
哀しみも切なさも、そうしてこの一夜限りの契りの後に当然訪れる苦しみも、そんな全てを背負うことを分かっていながら、それでも手を伸ばさずにいられない想いの重み。
生きることの残酷さを思ったとき、佐為は居たたまれない気持ちに負けそうになった。自分の苦しみは有ってしかるべきものだけれど…と。
そしてふっと視線を外してしまう。
「…夜が明けたら、全て忘れられるように…」
言いかけた唇を、思いがけない強い力で塞がれた。それは先ほどまで、硝子の破片であるかのような繊細さで自分の項を撫でていた行洋の唇。
熱に憑かれたような口接けはいっそ荒々しいほどで、濡れそぼって行く唇がまた新しい熱を生む。口腔を弄る舌の熱さは、驚きで一瞬見開いた佐為の瞳をそのまま閉じさせるほど。
「ん…んん…」
吸い上げられる唇の感覚に呼応して喉が鳴る。呼吸すら忘れたような激しさがそこにはあった。
ようやく解放された時には、圧倒的な力の差に恐れを覚えた佐為が身を震わせていたほどだった。
呼吸困難にも近い状況で、浅い呼吸をしながら佐為はこわごわ目を開ける。
「…忘れるなどと、そんなことは許さない」
厳しい瞳で見据え、行洋は静かだけれど強い口調でそう言った。
「見くびるな。そのようなこと、この塔矢行洋が望むように見えるか?」
その言葉を受けた瞬間、佐為は息を飲んだ。
これこそが、生きている者の強さ。そしてその前に、自分は平伏すことしかできない。
この強さを持ってして、今夜自分を愛そうというその想い。
喜びと、誇らしさ。切なさと、愛しさと…そして小さな悔い。
そんなすべてが綯い交ぜになったような感情が吹き荒れて、佐為は頭を小さく横に振った。
「ならば…もう考えるのはよそう」
表情を和らげて行洋がそう言ったとき、こみ上げてくるものを堪えきれず、佐為の目尻から雫が零れ落ちた。こめかみを伝い、髪へと流れ行こうとするその雫を今度は優しい力が遮った。
こめかみの薄い窪みでその涙を受け止める。目尻に、瞼に、濡れてしまった睫毛に、唇はそっと触れてゆく。
「…苦くないですか?」
辛い涙の味しか知らない佐為がそろりと呟くように尋ねた。あまりに優しく唇が、涙の線をなぞるから。
おや、というように行洋は少し眉を上げ、無垢な疑問をもった表情を見て、それから楽しそうに目を細めた。
「甘い…とてつもなく」
唇を重ね行く。触れるように一度、二度。薄く開いた唇は既に先程濡らされていたせいで、柔らかく行洋の唇を受け入れる。同じ形でしかない二つの部品を合わせていくことで成り立つ口接けは、決して完全に繋がることはできない。だからこそもどかしくもあり、そしてだからこそ激しさを増して、先を求めずにいられないもの。
口移しで味わった己の涙は、確かにとてつもなく甘いと、痺れ始めた頭の芯で佐為は思った。
蒼白ですらあった頬の色はうっすらと色づき、濡れた唇は艶をもって紅く染められた。
世にも儚い塗り絵のようだと行洋はこっそりと溜息をつく。
壊れものには手を触れてはいけないと、美術館では書いてある。しかしこれはどうだろう。
いまだその身体に纏わりついていた朱色の絹を奪い去ると、肌理の細かい肌が晒された。
一度は触れたその部分たちは、視界にあるがゆえに生々しく映る。
腰をきつく抱き締めながら、行洋がその胸元へ唇を寄せれば、漏れる吐息が色づいてくる。しこりを見せ始めたそこは、指先で押し込んでしまえるほど他愛もない存在。けれど吐息を吹けば素肌は張りを見せ、軽く噛めば瞬時に粟立つ肌がひどく感じていることを行洋に教えてくれた。
ふと見上げれば声を漏らすまいとしてか、下唇を噛み締める佐為の白い歯が映った。ぎゅっと両目を閉じて、拳に力を入れているらしく手首に筋が浮かび上がっている。
「佐為」
声を掛けても瞼も上がらない。
仕方なく行洋は身体を佐為の元まで戻して、ゆるりと抱き締め直した。固く閉じた唇に指で触れる。まだ濡れている唇はためらいを一瞬見せた後、薄く開いていった。指先をそっと歯の間に割り込ませながら、空いている手で胸元を弄る。
「あっ…はぁ…」
口腔に潜り込んでいる行洋の指を噛むわけにもいかず、佐為は切なげに鳴いて首を左右に何度か振っていやいやの仕草をした。行洋の指は既に充血した胸の突起に絡んでいて、尖った神経を休ませない。
ようやく口腔を支配していた指から逃れて、佐為は弱々しく行洋を睨んだ。
「…嫌…」
閨房での拒否ほど甘いものなどありはしないのに。
こんな子供騙しな照れ隠しをしてしまった自分が恥ずかしくなってきて、佐為はぷいっとそっぽを向いてしまう。
「いや?」
小さく笑ってからかうようにそう言うと、行洋は意地っ張りな横顔を見せた佐為の唇の端に口接けをひとつ贈った。その慈しむような許容に、くすぐったげに佐為は肩をすくめて泣き出しそうになりながら微笑んだ。
羞恥に目元を染め直したその笑顔は、今宵一番あどけなくも色めいたものだった。
白い腕が確実な意思をもって、行洋の首に纏わりついてゆく。触れるような頬擦りが通り抜け、唇が耳元にたどり着く。
「諸わなをほどいて…」
甘い声音で佐為がそっと囁いた。
濃い紫の指貫は未だ乱れもせず、まるでその下肢を護っているようだった。きつく結ばれた紐を息を飲んで引いて行く。きゅっと衣擦れの音が鳴り、白い上刺糸の下の蝶はその護りを解いた。
前布の緩みを感じ取った佐為は、今度は次を促すように背を向けて見せた。その仕草に合わせて流れ行く黒髪がさらさらと乾いた音を立てる。その流れから覗く肩から背、背から腰へと続くしなやかな線は、まるで秘密の共有を誘うように匂い立っていた。焚き染めた香が、肌が湿り気を帯びてきたせいで今そこにしかない香りとなって立ち昇る。
----この厳かな香りを、生涯忘れられはしないだろう。
行洋は心で呟きながら、佐為の背を護っていた最後の蝶を解き放った。
其の八
<其の七・備考>
諸わな…ちょうちょ結びのこと。
上刺糸…指貫の腰板部分の白い刺し糸