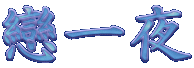
其の八
月下美人という花がある。
夏の夜、白く美しい花を一夜限り咲かせ、芳香を放ち、数時間で萎んでしまう。
そんな花に例えることさえ陳腐に思えるほどだけれど。
そう言ったなら、君は笑うだろうか
……それとも、泣くだろうか
薄暗がりに慣れた目が、生れ落ちた姿となった一夜限りの情人を色鮮やかに映し出す。
桜に染めた素肌の上に浮く、己が実らせた胸の果実のいっそ妖しいまでの薄赤。
その色づきを唇で辿り、中央線をなぞってゆけば、確かに彼もまた人の子であったという印へと行き着く。
小さく刻まれた窪みは、なぜかひどく愛しさを募らせて。
今抱いているこの躯は、夢でも幻でもあるけれど、真実でもあるのだと。
熱の気配を触れ合っている素肌が感じ取って、指を這わせて行く。白い下腹部は柔らかく指の腹に馴染み、そのまま脚の付け根へと近付くことを無防備に許す。
既に目覚めている雄の証が、そこに息づいている。同じ身体の造りであることを目で確かめて、それでもなお自分の内にある失われない熱。
太陽に当たったことなど一度だってないに違いない雪のような内股まで、掌を滑らせ行くと、ひんやりとした表面の冷たさが、掌の熱さに驚いたように震えた。
一瞬目を開いて行洋の存在を確かめた佐為の瞳の中で揺れる水。
今、彼に感覚の全てを与えるのが自分であるという実感が、行洋の嗜虐心をそそる。
不意をついて熱を放つ分身へと指を伸ばし力を加えると、針でつつかれたように佐為が大きく身を捩った。
「やっ…ぁ…」
眉を寄せた表情が、それでも苦しみではないものを漂わせているから、その反応は結局新しい熱を生むだけで。
掌の中の鼓動を確かめながら、顔を近付けて行く。視覚より先に嗅覚が、先端の溝に滲んだ透明な雫を認識した。舌先だけでその苦味を生む先端を掬うように舐めとりながら、片手で自身をきつく握ってやると、佐為が背を反らしてもはや声にならない掠れた吐息を漏らした。
そのまま神経が剥き出しになったそこを唇で包めば、行洋の思惑通りに佐為が華奢な脚を力なくばたつかせて逃れようと試みる。その僅かな抵抗すら許さず、片手で身体を押さえ込めば、もはや身体を仰け反らせて声を夜に溶かし行くより他に佐為に道はない。
そうでなくとも、千年ぶりに与えられた肉体。
快楽の受け止め方などとうに忘れてしまっているし、逃れ方すら覚えていない。
与えられる愛撫にただただ流されることしかできないで、触れ合う素肌に嬌声をあげずにいられない自分を恨めしく思うより他に術もなく。
どんどん追い上げられて行く躯の熱の持って行き場所も分からないで、苦しいとすら思う。
「…あっあっ…」
指と舌で締め上げられる感覚が劣情を募らせる。張り詰める自身と裏腹に緩んだ涙腺が目尻から濡れた線を描き行く。湧き上がって行く熱が出口を求め始めていることを、行洋も悟っているらしく、愛撫は激しさを増していた。指がしがみつく先を探して、床へ畳へと彷徨っては爪を立てる。その手を行洋の片手が捕まえた時、佐為の最奥の熱が大きく動いた。
「…も…離して…」
この世で一番甘い投了の言葉を、それとは知らず絞り出していた。
荒い呼吸を繰り返す背を撫で、力の入っていない身体を抱き締める。
汗ばんだ肌はしっとりと濡れていて、茹でたようにしなやかに手に馴染む。乱れた髪をそっと手で梳いて行くと、まだ恍惚から抜け出せないように潤んだ瞳がゆっくりと開いた。夜の中、月から隠し、それでもなお輝くまなざしの光はぼんやりと行洋を見上げてくる。
しばらくの躊躇の後、行洋は自らの口中で濡らした指を白い双丘の狭間へと滑らせた。
ぴくりと腰が震え、一瞬にして素肌が張りを取り戻す。たった一本の指の浸入にすらむずかるような筋肉の収縮を見せ、そこは行洋に狭隘であることを誇示してきた。
「・・・佐為」
目を閉じているその睫毛の震えまでもが見えるようで、行洋は吐息を吹きかけるようにその名を呼ぶ。
「嫌か?」
「いいえ、いいえ、違っ・・・」
慌てて否定しようと目を開いて、身を捩ったその行為で、咥え込まされた指の感覚が躯の中に刻み込まれる。
既に自分は捕らえられている。
その実感は、一度達した躯に新しい熱の波を生み始めていた。
きゅっと力が篭った手が、自分にしがみついてきたのを感じて、行洋は愛撫を再開する。
「・・・んっ・・・ふ・・・」
軽い痛覚の中を、たまに快感が過ぎって行く。たった一本の指の浸入さえ拒もうとした内壁は、いまや抜き差しをゆるりと受け入れるまでにほぐされてきている。振り子のように、不快感にも似た苦痛と蕩けそうな快感の間を、神経がいったりきたりしていた。
狭さばかりが気になってしまっていたその場所で、あたらしい滑りをその指先に感じて、行洋は時機を逸せず指を増やす。
「・・・つっ・・・」
今度ばかりは痛みを堪える声がして、佐為が腰を引いた。二本の指は深く入り込んで、しばらく時を待つ。
抱きしめていた手で頤に触れて、行洋は佐為の顔を上げさせて口接けた。ゆっくりと下唇を噛み、緩やかに唇を開いて応じる佐為の口腔へと舌を滑り込ませる。
上も下も唇を塞がれている状態に、痺れるような従属感が背筋を駆け下りていった。それはまるで甘い鎖のように佐為の感覚を締め付ける。
「ん・・・んんっ・・・」
細い喉を鳴らしてゆけば、長い口接けに唇の端から雫が零れ落ちてゆく。時を同じくして、下界から消えた二本の指が動き始めた。ゆっくりと、でも拡がりを要求する動き。
探るような指先の動きが、不意にその場所を探り当てた。佐為の中の振り子が、快感の側に振り切った瞬間でもあった。
「やっ・・・ぁ・・・」
抗うことのできない倒錯感が全身を駆け巡る。もうなす術もなく、佐為は行洋の身体にしがみついてゆくばかり。
決して蹂躙されているわけではないけれど、快楽の全てを支配されている感覚は恨めしくもあって、佐為はせめてもの抵抗であるかのように、目の前の肩に噛み付いてみる。けれど相手はそんなことは意にも介さないようで。
鳴き声が示したその場所を、行洋はやんわりと攻め上げる。近付いては離れ、また近付いて。
そうしているうちに、秘部はいつしか行洋の指を誘い込むように蠢き始めた。
最後の合図に咥え込ませた指達を、そこは包み込むように受け入れる。柔らかく濡れた粘膜は、もはや指先の持っていた熱と同じ熱さを孕んでいた。
うつ伏せになるよう、促した手の動きに佐為は素直に身体を反転させてゆく。流れ行く黒髪が徐々に現す無防備な背中の白さを彩る。
緩やかに反らされた背中の曲線は、もはや行洋に何の迷いも与えなかった。
ゆっくりと押し出す腰の動きに、佐為は必死に腰を引かないように歯を食いしばる。押し当てられる熱い塊を目一杯感じながら、ぽろぽろと涙を零して痛覚に耐える。
「・・・くぅ・・・」
つい漏れてしまう苦悶の声に、気遣うように行洋は動きを止める。そうして佐為の中の痛みの波が静まるのを待ってから、静かに静かに、分身を埋めて行く。
行洋のそのままの熱さが自分の中に入り込んでくる過程を、痛みの中ですら佐為はいとおしく想って涙ぐむ。
欲望のままに突き上げてもおかしくないその状態で、それでも大事に自分を扱う優しさ。
その感情がもし色彩をもっていて、自分の視界に広がったなら、もうそれだけで果ててしまうに違いない。
ようやく全てを飲み込んだときには、佐為の躯のほうが蕩けて動きを求めるほどだった。
ゆらりと揺らめく腰の動き。刺激を求めるようにひくひくと痙攣する入り口。
何もかもに誘われて、行洋は目の前に白く浮かんだ腰を掴んでゆく。
「あっ、・・・んっ・・・」
制御を失った佐為の唇が甘い声を漏らし、行洋の視界の中、助けを求めるように伸ばした指が寝具の端を引き掴む。その指の動きすら自分へと向かわせたくなる雄の独占欲がそそのかすままに、行洋はふっと躯を離した。慌てたように振り返った佐為の、瞳の中の動揺がますます情欲を昂ぶらせる。
「・・・顔を見ていたいから・・・」
耳元に言い訳めいた囁きを落とし行けば、佐為はこっくりと頷いてその身を行洋に預けてくる。白い脚がゆるゆると行洋の腰に絡んでくる様は、雄の征服欲を満たして余りある光景だった。
再度繋いだ躯を確かめるように、行洋は床に手をついて腰を突き上げる。
「痛っ」
突然佐為が驚いたように声を上げた。見ると自分の手の下に黒髪が数筋敷かれていて、己の逸り具合に行洋は苦笑いした。
「・・・すまない。でも君が逸らせるから・・・」
「ひどい、私のせいにするのですか?」
大袈裟に唇を尖らせるいとけなさに、行洋は胸が詰まるような苦しさを覚えた。組み敷いた躯は、無防備に行洋に向かって開かれている。思わず降らす口接けの熱さに、同じ熱さで応えてくるまっすぐな愛情がただひたすらにいとおしかった。
抱き締め直し、もう手加減など出来ずに楔を打ち込む。
「あぁっ・・・ん、・・・はあっ・・・」
弓なりに背を撓らせながら、佐為が酸欠の魚がするように口を動かす。その唇に湛えられた蜜に誘われて、また唇を重ねゆけば、入り混じった互いの熱が夜に溶けて行く。
白い寝具の海の上、二人は互いを繋ぐ生身の鎖に思う様溺れて行った。
其の九
<其の八・備考>
狭隘…きょうあい。狭いこと。