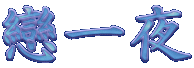
其の五
逢ひ見ての のちの心に くらぶれば 昔は物も 思はざりけり
---- 藤原敦忠
「石を持ったのは、実は千年ぶりなんです」
楽しそうに終局図を覗き込みながら、佐為は声を弾ませた。
打ち切った盤面は、行洋が今まで打ってきたどの一局よりも美しく仕上がっており、大きな充足感と高揚感を二人の間に呼び起こしていた。
「いいものですね、やはり…」
しみじみと、身体の奥底から漏れてくるような言葉だった。行洋は相槌すら打てず、ただ受け止める。千年とさらりと言う彼の、永い時間を想像する力すら自分にはないと、行洋は思う。
「ありがとうございました」
佐為は両手を膝の上に乗せて、丁寧に一礼した。
「あなたの祈りが強かったから、あなたのおかげで石を持って打つことができた。…ありがとう、塔矢行洋殿」
蒼い月が降り注ぐ。瞬きをするたびに睫毛の影が頬で揺れる。
真っすぐな感謝の眼差しが向けられていた。
その純粋さになぜかチクリと胸が疼くのを行洋は感じた。
舌の上に、苦いような甘いような何かがのっているような感覚が離れない。
「また…」
ひとりでに動き出した唇は、自制する方法を失っていた。
「またこうして打てるのだろうか?」
どこかで答えを知っているのに。
行洋は歯噛みしたい気持ちで、勝手に吐き出されてしまった言葉の先を追った。
「……さあそれは…」
小首を傾げて佐為は寂しげに微笑む。
夜風が少し強く吹いて、長い髪の裾を揺らしていた。
それが答えだった。
全ては今宵一夜のこと。
行洋は心が波を立ててくるのを感じていた。
このざわめきの感触は、まるで初めてでありながら、懐かしさも併せ持っている。全く知らない感情というわけではなかった。
奥歯が震えるような感覚に襲われて、思わず歯を食いしばる。
惹かれているのだ。
自分は目の前の藤原佐為という者に惹かれている。
それは、とてつもなく甘い敗北感と恐怖。
----夢ならば、ここで私が盤を超えて手を伸ばしても、良いのではないだろうか
その思いつきは、狂おしいほどの誘惑となって、行洋の中を駆け巡る。
「…行洋殿?」
おずおずといった口調で、佐為が問い掛けてきていた。不安気に下から見上げてくる目線が痛かった。
「すまない、盤面に見入っていた」
両手を袖の中に互いに差し入れながら、平穏を装う。
「いえ、あの…随分と怖い顔をしていますよ?どうかされましたか?」
こうして終局した状態で向かい合うと佐為は随分幼く見えると、行洋は思った。 碁を打つときの張り詰めた糸のような厳しさは皆目見当たらず、端正な顔立ちで瞳をくるくると動かす様は、彼が持つ表情の引出しの多さをちらりと教えるようだった。
この問い掛ける薄い唇を啄ばんだとしたら、どのような表情が咲くのだろうか?
息苦しいほどの想いが、その発想を生んで、急速に体温を上げて行く。呼吸がどんどん浅くなってゆく。自分の汗ばんだ掌を袖の中で握り締めて、行洋は視線を上げた。
何をどう隠したところで、空から来た相手に通用するはずがあろうか。
その考えは、胸のつかえをすとんと落とした。
「苦しい…というと、君は笑うだろうか?」
想いを一欠片、吐露してみる。
生真面目に首を横に振って、佐為は「いいえ」と小さく返事をした。やや短い幾ばくかの髪が、その動きに合わせて肩を撫でる。
「今夜まで私は、ひどく苦しんできたと思っていた。もう一度、saiと対局したいと…叶わない願いかもしれないということが、分かっていたから苦しかった。でもそれが叶った今…君と逢えた今…違う苦しみがここにある」
小さな声でも十分伝わる距離。
呟くように想いを並べて見せた後、行洋は静かに胸に手を当ててみせた。
そのままゆっくりと、盤上の向こう側に目を向ける。
唇を噛み締めて、今にも泣き出しそうな表情の佐為が、そこにいた。
「…苦しい…だけ…?」
蒼い月光は夜の深まりとともに青白さを増し、それは惜しみなく地上の夜に降り注がれている。
佐為の瞳は水分を増している分だけその蒼さを多く映して、新しい光を生み出していた。
相手に苦しみしか与えない恋なら哀しすぎる。
こんな風に苦しみを開いて見せられることで切なさを感じるのは、初めてかもしれないと、佐為は思う。
自分だけを見てくれる相手と向き合うことなど、佐為のこの千年にはなかった。
もしかしたら生前にはあったのかもしれない。けれどもう、それは遥か彼方の景色。輪郭すら思い出せないぼやけた記憶。
今、行洋は静かに自分だけを見詰めている。確かな熱をもった瞳で。
それは千年もの間眠っていた、躯の熱を呼び覚ますには十分な力を持っていた。
どうせ一夜の夢なのだ。
朝になれば消え行くさだめ。
欲してくれている人がそこにいて、その魂の呼び声に応ずることが、そんなに悪いことでもないような気がしてくる。
限られたこの空間と時間を、想いだけで満たしてゆけば、そこに残るものは何か。
例えばそれを見極めることで、この命が真の意味で途切れるのであれば、それも悪くないとすら佐為は思った。
「行洋殿」
次は佐為が想いを開いて相手に見せる番だった。
ふと、ここでも自分は白番だろうかと思いつき、佐為は微笑む。
それなれば、次は負けないようにうんと強い手を打たなければ…と。
立烏帽子に手をかける。笛のとなりにそろりと置いた。
盗み見ると、行洋の驚いた表情が視界に入る。
けれど彼は知る由もない。烏帽子を外すということが、平安貴族にとってどれほどの意味をもつかなど。
佐為は行洋の表情から、まだ自分の一手の真意を理解していないことを見抜いた。
虎次郎と過ごした時ですら、人々は被り物をしていなかったのだから。
だからそのまま流れるように、烏帽子から離れた手を首元へとやって、蜻蛉を受緒から外した。
「もしも苦しいだけでないならば…一時私を月から隠してください」
囁きは放たれた。
其の六
<其の五・備考>
蜻蛉…とんぼ。狩衣の首もとで繋ぎ合わせる玉の部分。
受緒…とんぼを留めるための輪の部分。