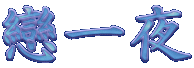
其の四
太陽は眠り、星々は夜に抱かれ、月は闇を斬らずに盤上を照らす。
そして世界は目を閉じる。
選ばれしこの瞬間達を、許されたこの邂逅を、黙認せんがために。
白い指先が白い碁石を挟んで打ち込む。
月光を纏って、その動きはきらきらと輝きを放つ。
まるで絵が動くように優美なその動作は、前回の対局で行洋が感じた古豪の持つべき霊妙な気を理由づけるのに十分だった。
盤面は過去のどの対局とも似ていない棋譜を描いていき、それはまるで川の流れのようだった。
石達はまるで行洋が始めに放った黒石を水源とするかのように、海という終局に向かって流れ行く。
途中、滝のように激しい流れを経て。
せめぎ合う黒石と白石が織り成す模様は、まるで水が打ち付けられて飛沫をあげる様。
相手の一手を睨み、表情を読み、そしてまた自らの一手を繰り出す。
流水は黒に流れ、白に傾き、うねりを帯びてゆく。
形勢は互角。
行洋が打った妙手が、流れをやや黒に手繰り寄せようとしていた。
唇を噛み締めていた佐為が、不意に隣に置いた笛を手に取った。そのまま両手で持とうとする仕草をして、ぴたりと動きが止まる。
「……」
はっとしたように手元を見つめて、佐為は恥ずかしげに頬を染め、両手で笛を握り締めた。 集中したあまりに、手放した扇子の存在を失念していたのだった。
そう、既に自分は託したのだ。
その想いは、今はもう、佐為を微笑ませることができる。こんな厳しい一局の最中でさえ、思い出は佐為を温かく包む。
唇は柔らかな曲線を描き、月を仰ぎ見る瞳はその光を宿した。
再度盤上に視線を移す。
激流に飲まれそうになっている白石の流れにもう一度身を置く。そうすると、新しい風が吹いてくる。
ピシリと小気味いい音を立てて打ち込まれた一手に、行洋は息を飲んだ。
「これはまるで…耳赤…」
盤面と佐為を見比べて、思わず零れ落ちた一言。
冷たい汗が背を滑り落ちるのを感じながら、行洋は目前の相手を凝視する。
その視線の意味を悟り、疑問を交わすように、佐為は肩をすくめて見せた後、幼子のように表情全てで笑って言った。
「けれどあなたは幻庵殿より強いではありませんか」
これ以上の言葉を必要としない、答えであった。
その豪胆でさえある言葉と、悪戯をするような仕草につられ、行洋も低く笑った。
いくつかの過流を過ぎ、流れは力強くなっていき、大ヨセの局面は静かに川下へと向かっていた。
海が、もうそこにある。
細かいヨセだったけれど、行洋の望んだ海が、視界に開けようとしていた。
「…一目半足らず…ですかね」
唇を尖らせて、悔しそうに佐為が呟いた。
同じ海を、二人は見ていた。
佐為がすっと背筋を伸ばしたことで、頭を垂れようとする前触れを見て取り、行洋は反射的に口を開いた。
「待ってくれ。最後まで…」
----最後まで、打ち切ってくれないか。
そう言いかけて、自分の言葉に驚く。
…川はもう、終わっているのに。
「すまない、無粋なことを」
素直に詫びた言葉の真っ直ぐさに、佐為は緩々と頭を横に振った。
「いえ、私のほうこそ。…せっかくですから、この美しい絵を完成させましょう」
もう少し打っていたいという、その想いは佐為とて同じ。
いつしか月明かりには蒼みがかかり、盤上の静かな波を照らしてゆく。
僅かな風が、伽羅の香りを行洋の鼻腔に届ける。
盤上が19路しかないことを、なぜか行洋は寂しくすら思った。
たった361目。
いつもは果てしない宇宙のように広く感じるその空間は、佐為と埋めていった今、一枚の絵となっていた。
其の五
<其の四・備考>
邂逅…かいこう。 思いがけなく出会うこと。めぐりあうこと。
耳赤…「みみあかの一手」のこと。その一局自体を「耳赤の局」とも言う。
対井上(幻庵)因碩戦で放たれた本因坊秀策の歴史に残る妙手。
15巻中、棋院でヒカルが見ていた秀策の棋譜の黒127手目である。
過流…かりゅう。渦巻く流れ。